「自分のことがわからない」時のヒント

自分のことがよくわからない時ってどうしてますか?
心理テストやタイプ分けの性格診断なんかをやってみる人もいるかもしれません。
何が好きで、何が嫌いか、得意なことや苦手なことなど、自分のことがはっきり分かれば仕事選びもスムーズで、普段の生活も充実して密度の濃いものになりますよね。
ここでは自分のことを知るためのヒントをお伝えします。

自分がわからなくなる理由
まずは自分のことが分からなくなる理由からお話ししたいと思います。
「自分」とは多くの場合はセルフイメージを指すのではないでしょうか。
セルフイメージとは「自分はこういう人だ」という自己認識です。
でも、実際にはそれ以外にも自分の要素があったり、セルフイメージそのものが揺らいだりします。
まだ知らない自分がいたり、たまに顔を見せる自分がいたりしてはっきりしないのですね。
また、本来の自分とはかけ離れたセルフイメージをつくっている場合もあります。
幼少期に受けた親や学校教育の影響で本来の自分とは違う自分を自分だと思い込んでいることが原因です。
この場合はいくら考えても自分のことがよくわからないという状態に陥ります。
親の理想の自分になろうとしたり、学校で馴染むために周りに合わせたりしているうちに本音がわからなくなってしまうというパターンが多いでしょうか。
自分を知るための2つのベクトル
では、自分を知るためには何をしたらいいのでしょうか?
基本的にはセルフイメージを本来の自分に近づけるということになります。
それには2つのベクトルがあります。
1つはまだ知らない自分を見つける、自分再認識のベクトルです。
何気ない習慣の中に埋もれてしまった好きなことや自分の気質を再認識することです。まだセルフイメージには入っていないけど自分の要素にあたるものを認識することでセルフイメージを正確にします。
自分を再認識できるような質問に答えたりするのが一般的かもしれません。就職活動や転職活動でする自己分析にこの要素は多く含まれています。
もう1つは間違って作られたセルフイメージの訂正です。親や学校の影響を受けてセルフイメージが作られているため、その影響による勘違いに気が付き、影響を緩めることで本来の自分を発見するというベクトルです。
多くの場合、本当の自分は「やらなきゃ」「こうあらねば」に埋もれてしまっています。
「やらなきゃ」を緩めていくことで影響を受ける前の本来の自分を見つけることができます。
ちなみに、最初のベクトルの方が簡単です。うまくいけば発見がたくさんあるはずです。
それだとピンと来ない場合は後者を扱っていく方が効果的かもしれません。
2つのベクトルを分けて考えておけばいくら考えてもわからない、ということがなくなります。

自分を知るためのヒント(自分再認識編)
観察する
まずは自分を再認識するベクトルからみてみます。
再認識するのに必要なのは自分を客観的に観察することです。「そういえばよく塩胡椒で味付けしてるなぁ」とか「いつもコーヒーはブラックだなぁ」とかそんな感じです。
よくしている選択に意識的になってみるのです。
たとえば、同じ店に行きがちなら「確実さや安定」を求めるタイプかもしれません。毎回違う店に行くなら「好奇心旺盛」なタイプなのかもしれません。
友達に聞いてみる
自己分析の定番とも言えるものですが、友達に自分はどんな人か聞いてみましょう。
何人かに聞くと傾向が見えてきたり、新しい発見もあるかもしれません。
自分史を書く
今まで起きた出来事を振り返ってみます。
その時どんなことを感じていたか、振り返りながら作ってみると自分を知る手がかりになります。
幼い頃の出来事もヒントになる可能性があります。

自分を知るためのヒント(勘違い訂正編)
ここからは勘違いして作られたセルフイメージの訂正のベクトルです。
成長過程でいろんな影響を受けた自分を自分だと勘違いしていて、本来の自分が見えない状態です。
影響を受けた自分は「やらなきゃいけないこと」をやろうとする傾向があります。それが本来の自分をわからなくさせています。
まずは「やらなきゃいけないこと」を見つけます。
その「やらなきゃ」を緩めることが幼少期の影響を緩めることになります。
影響を受けた自分を見つける

方法① 周りの大人に言われたことを振り返る
まずは比較的簡単な方法です。
小さい頃言われたことで印象的なことはありますか?
「〇〇しなきゃダメでしょ!」
「早くしなさい」
など、言われた言葉がセルフイメージを作ることがよくあります。
「◯○やらなきゃ」「自分は遅いんだ。早くしなきゃ」
という感じです。
言われて印象的だったことやよく言われていたことを思い出してみるとヒントが隠れているかもしれません。
方法② 「やらなきゃ」に意識を向ける
あんまり気が向かないけど「やらなきゃなぁ」と思っていることってありますか?
「生きるためには働かなきゃ」「ちゃんとやらなきゃ」「努力しないと」
など、本音と違うところはないか見てみます。
やらなきゃいけないことをやるうちに、それをやる自分が自分だと思い込んで本来の自分がわからなくなってしまいます。
方法③ イライラのポイントを探る
「やらなきゃ」と思っていることが見つからない場合は人にイライラするときを思い出してみてください。
イライラって煩わしいですが、自分を知るためのいいツールです。
自分が「やらなきゃ」と思っていることを相手がやらない時にイラっと感じることがあるからです。
イラッとしたら、相手は本来どうすべきか考えてみます。それがそのまま自分自身にしなきゃいけないと課していることです。
「気を使うべき」「愛想よくすべき」と思うなら自分に「気を使わなきゃ」「愛想よくしなきゃ」といつも言っているということです。
自分が頑張ったり我慢したりしてやってることを平気でしない人がいたら「やれよ!」ってなりますよね。
イライラのポイントから自分に課していることを探してみましょう。怒りが強いほど「やらなきゃ」も強いということになります。
影響を緩める

方法① 問いかける
「やらなきゃ」が見つかったらそのこだわりを緩めます。
まずは本当にしなきゃいけないことなのか考えてみます。
それでもしたほうがいい感覚があれば、つぎの方法へ進んでみてください。
方法② 見方をフラットにする
そのこだわりを持っているメリットとデメリット、フラットに見てみます。
「愛想良くしなきゃ」だったら愛想を良くするメリットとデメリットです。
例えば
メリット→周りに好かれる、みんなが笑っていられる、嫌われない…
デメリット→疲れる、自分が頑張っても空気が悪くなる可能性、誰にでも好かれるわけではないので無駄な努力、など
見方をフラットにするとそんなにやらなくてもいい気持ちの湧いてくる可能性があります。
方法③ 想像してみる
もしそれらを全くしなかったら、どんなことをしていると思いますか?
できるだけたくさんの可能性を想像してみます。
それを実際に行動に移してみてもいいかもしれません。
ちょっとハードルが高く感じるかもしれませんがこだわりとは逆の行動を取ってみるのも緩める方法の1つです。
想像するだけでも構いません。
想像しているうちに、そんなに頑張ってやらなくてもいいかな、と思えたらうまくいっています。
本音と本来の自分を育てる

やらなきゃいけない感覚が少し緩んできたら、次は本音を見つめてます。
今までないがしろにされていき本音を大切にすることで、本来の自分を育てていきます。
本来の自分は本音が大切にされた状態の自分のことです。
「やらなきゃ」を支える感情を見つめる
強いこだわりって自分の価値を証明するものだったりします。
「よく気がきく人でいなければ」と気遣いをして、優しい声かけや明るい挨拶を一生懸命していたとしたら、優しくて気がきく自分が価値があると感じているという感じです。
自分の価値を感じるために「やらなきゃいけないこと」をやる可能性があるのです。
なんでそんな風に思うのか耳を傾けてみることは本音を聴くことでもあるし、「やらなきゃ」を緩めることにもつながります。
価値を認めて欲しいと感じる感覚や感情も自分の本音のひとつにあたります。
本当にしたいことに耳をすます
「やらなきゃ」が緩んでくると本当はどうしたかったのかを聴くことができます。
少し長丁場かもしれませんが、価値を認めて欲しい自分のネガティブな感覚や感情も含めて、本当はどう感じているか耳をすましてみます。
いままで「やらなきゃ」「こうあらねば」に消されてしまっていた本音を育てていくことで、本音を元に本来の自分を育てていくことができます。
その育った自分が正確なセルフイメージとなります。
「やらなきゃ」を緩めつつ、本当の自分が顔を出して育っていくことを楽しんでみてはいかがでしょうか。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








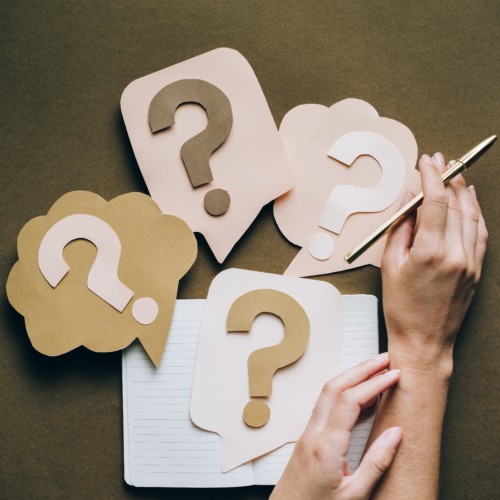



この記事へのコメントはありません。