やる気はあるのにできないのはなんで?自分で決めたことを続けるコツ

この記事でわかること
・やる気はあるのにやりたくなる理由
・習慣化に必要な意識
・習慣化のコツと知っておきたいこと
「やろうって決めたのに、やりたくないーー!!」
「自分でやりたくて決めたのに」
「やる気はあるのに」
その日も私は寝る前に引き裂かれるような気持ちになっていました。
アクセルを踏みながらブレーキを踏むような感じでした。
ストレッチが気持ちよかったから毎晩やって寝ようって思ったのに、なかなかできない日が続いていた時のことでした。
なぜか気が重くなっちゃうというか、やりたくなくなっていました。
布団の上で
「もう諦めて寝ちゃおうかな」
「いや、でもやりたいな」
「なんでこんなにやりたくないんだろう」
さっさとやればいいのに(笑)考えているうちに時間だけが過ぎていきました。
やる気はあるはずなのに、なぜか行動に移せない
自分で作ったTODOリストに押しつぶされる気持ちになってしまう
私が自分で決めたことを続けられない理由は心の奥にありました。
この記事の目次
できない理由は前向きな気持ちに隠れている
 TODOリストを作ったり、やろうと決めたのにそれができないのは原動力に自己否定が入っていたからでした。
TODOリストを作ったり、やろうと決めたのにそれができないのは原動力に自己否定が入っていたからでした。
「よくなろう」
「自分を磨こう」
「素敵な人になりたい」
「変わりたい」
私は向上心の強いタイプだったのですが、その向上心は、自分の現状に対しての不満や変わりたい気持ちから来ていました。
「もっと自分をよくしよう」その前向きな気持ちの中に自分への不満や否定感が隠れていたんです。
だから、よく挫折していました。
英語の勉強に挫折したり、ストレッチの習慣化に挫折したり…
英語勉強しよう
もっと体力つけよう
って気持ちは、もちろんポジティブな気持ちもあるけど、今の自分に満足できないから何かしたい、変わりたい、というのもありました。
だから極端に表現するとこんな感じでした。
「今の自分じゃダメだから」英語勉強しよう
「今の自分じゃダメだから」もっと体力つけよう
(極端すぎるけど、、まぁ、わかりやすく言うと!笑)
そうすると、
英語を勉強するたびに「今の自分じゃダメだ」
ストレッチするたびに「今の自分じゃダメだ」
って繰り返すことになってしまったんです。
これが、私が決めたことが続けられない理由でした。
毎回、ダメだダメだと言われていたら、やりたくなくなるのは当然ですよね。
でも、英語を勉強したいのも、ストレッチも本当にやりたいことではありました。
ここでは、楽しく続けるために考えるべきだな、と思ったことをまとめました。
原動力を確認しよう
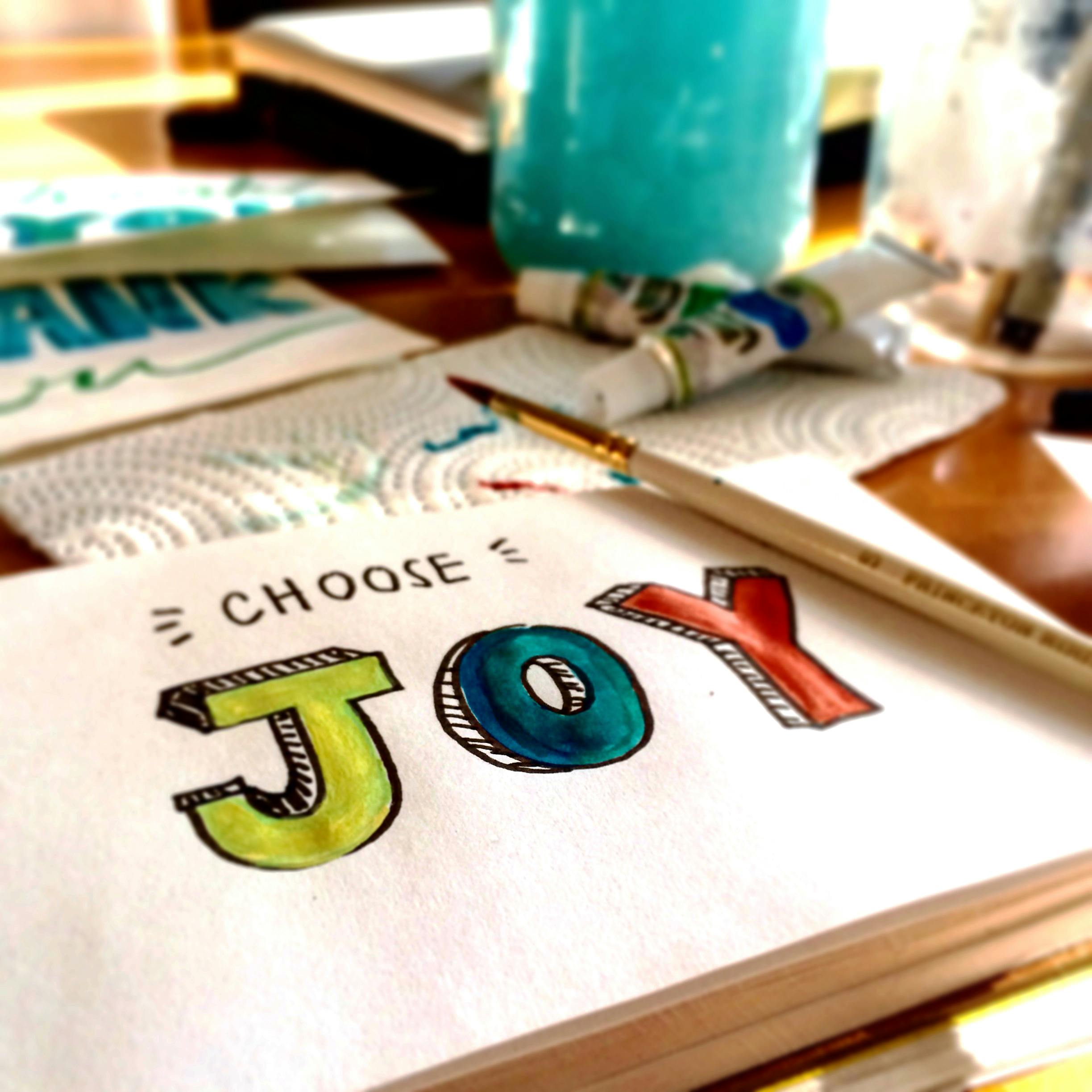 「今の自分じゃダメだから」という欠乏感や自己否定が原動力になっているのか
「今の自分じゃダメだから」という欠乏感や自己否定が原動力になっているのか
「もっとやりたい」というポジティブな気持ちが原動力になっているのか
それが続けられるかどうかの分かれ道です。
分かりやすく言うと前者は「やらなきゃ」後者は「やりたい」です。
続けるためには、原動力をポジティブなものにしておく必要がありました。
原動力をポジティブにするためには「やりたい」と思ったその時の気持ちをちゃんと覚えておけるかが勝負です。
ストレッチならストレッチした時の心地よさ
英語なら英語を学んだ時や英語で話した時の楽しさ
「いいな」「やりたいな」具体的で体感的なものをいつも原動力にするようにしました。
そうすると「やらなきゃ」にならずに「やりたい」のままいられることが増えました。
目的を確認しよう
 他にも「やらなきゃ」にならずにいられるポイントがありました。
他にも「やらなきゃ」にならずにいられるポイントがありました。
それは目的を確認することです。
目的を設定して、そこに向かっていくのって窮屈で嫌いだったんですけど「目的決めるのっていいな」って最近は思います。
目的って言うと大袈裟な感じしちゃうけど、例えば
ケーキ食べたいなーと思ったときには「自分を満たすこと」が目的だったり
自然の中でのんびりしたいなーって思った時は「リラックスすること」が目的だったり
案外、身近に転がっているものなんですよね。
それで、これがちゃんと掴めていると人生の満足度って急激に上がるって感じるんです。
よく手段が目的になってしまうことってあると思うんですが、そうなると人って「やらなきゃ」になってしまいます。
例えば英語学習です。
海外旅行に行ってお店の店員さんと世間話した時、本当はもっと話したかった。
次は英語力をつけて海外旅行に行きたい。
海外に友達できたら楽しいだろうな。
と思った場合の目的は「英語でコミュニケーションをとること」になります。
ここを忘れなければ「英語でコミュニケーションをとるために英語を勉強しよう」となるわけですが、目的を忘れるとそうはいきません。
英語を勉強すること自体が目的になって「毎日単語を少しずつ覚えなきゃ」「英語字幕で映画を見ないと」となんてタスクに追われる感じになりかねません。
目的を見失った時「やりたい」は「やらなきゃ」に変わります。
目的は原動力とやる気の行き先なので、目的がぶれてしまうと、やる気は行き場を失ってしまうのです。
プロセスを大切にする
 もう一つ、私が継続する上で、「効いたなー!」と思うのはプロセスを大切にすることです。
もう一つ、私が継続する上で、「効いたなー!」と思うのはプロセスを大切にすることです。
結果を重要視してしまうと、結果が出ている「未来の自分」はいいけど、結果を手にしていない「今の自分」はダメ、になりやすいからです。
原動力がネガティブだと陥りやすいのですが、目的がはっきりしたとして、結果や成果をあまりに期待するのはけっこう辛いことです。
結果はプロセスの積み重ねなので、プロセスがしんどいと、結果もしんどい=なかなか結果が出ないという感じになりやすいです。
目的に向かうまでのプロセスそのものを楽しめるかどうかを確認しておくのがおすすめです。
続けるためのチェックポイント
続けるためのノウハウはたくさんありますが、目的がちゃんと確認できていて、ポジティブな原動力でそこに向かうことができないと、どれだけ続ける工夫をしてもなかなか続かないものです。
だから続ける工夫よりも目的と原動力を確認してポジティブなやる気がスムーズに目的に迎える状態を作っておくのが最優先です。
そして結果は関係なく楽しいと思えることです。
これが揃ったら続けられる可能性はぐっと上がります。
チェックポイントはこちら。
- 原動力はポジティブなものか
- 目的は何か
- プロセス自体が楽しめるか
ぜひチェックしてみてください。
続けるための習慣化
さて、最優先事項を確認したら、習慣化について考えてみたいところですよね。
朝のルーティンすら存在しない私が「これはよかった」と思う習慣化の方法を書いておきます。笑
自分を観察して習慣を作る
 生活の中で何気なくしていることの延長線上に、上手に新しい習慣を組み込んでいく工夫ができたことは楽に続きました。
生活の中で何気なくしていることの延長線上に、上手に新しい習慣を組み込んでいく工夫ができたことは楽に続きました。
毎日、当たり前に毎日していることって無理なくできるから続いていることでもあるんですよね。
だから、そこに新しい習慣をなるべく自然にくっつけます。
自然に、というのは今までの習慣の一部を新しい習慣に置き換える感じです。
例えば、英語をアプリで勉強しようと思ったら、何気なくスマホを見てしまうところに組み込みます。
朝の通勤中、何気なくSNSを見ている時って、すでにスマホは持っている状態なので、SNSを英語学習に置き換えるだけで新しい習慣を取り入れられます。
スマホを見る、という習慣はすでについているから内容だけ置き換えてしまえば組み込みやすいのです。
「〇〇したついでにやるって決めておく」って技も本で読んで試したのですが、元々してることと、新しい習慣が関係なさすぎるとあんまり続かなかったんです。
自分をよく観察して、自然に新習慣を組み込んでいくのが重要でした。
そうそう!
習慣を作る時に重要だと思った意識があったので、それも書いておきます。
重要な意識
 自分を観察して習慣を作っていく時、習慣作りを邪魔した視点がありました。
自分を観察して習慣を作っていく時、習慣作りを邪魔した視点がありました。
それは
「無駄を省こう」
「もっとできるはず」
「徹底的に組み替える」
どれも今の自分を否定することになってしまうからです。
とにかく否定感は行動を止めるので、やめておきたいところです。
今の生活はそれでいいし、変える必要は一切ない。
その認識を持った上でどこに新しい習慣を組み込むのがスムーズなのか考えてみることをおすすめします。
うまくいったケースをストックする
 色々試行錯誤していく上で、うまくいくこと、うまくいかないこと、どちらも出てきました。
色々試行錯誤していく上で、うまくいくこと、うまくいかないこと、どちらも出てきました。
その時に「なんでできなかったんだろう?」と考えるよりも「なんでできたんだろう?」って考えた方が圧倒的に結果が出ました。
「なんでできなかったんだろう?」って自分を否定しながら考えることになるのであんまりクリエイティブな答えが期待できません。
「なんでできたんだろう?」はできるコツを体験から抜き出して活用できます。
つい「なんでできなかったんだろう?」「なんでダメだったんだろう?」考えちゃうものだけど、、
「なんでできたんだろう?」「何がよかったのかな?」は口癖にしたいくらいだなぁと思います。
変わりたくない!潜在意識の見えない力
これを知っておくと、案外習慣を作る時に役立つ知識が「心のホメオスタシス」です。
この「ホメオスタシス」、中学の理科で習ったの覚えていますか?
ホメオスタシスは体の状態を一定に保つための恒常性のことです。
心にも同じように今の状態を保つ力が働いています。
これはエゴ(短期的な防衛本能)によって変化から自分を守ろうという働きかけでもあります。
それに加えて、心は変化を恐れる傾向があります。
なんで心が変化を恐れるかというと、人生で1番最初に経験する変化、出産の印象がネガティブであることが多いからです。
生まれてくる時に子宮の伸縮によって呼吸が止まること、狭い産道を通ること、外気や眩しいライトなどの刺激、生まれてすぐ母親から離される孤独感、、赤ちゃんが苦しさや怖さを感じる要素って案外たくさんあります。
この最初の変化をネガティブにとらえてしまうと、その後の変化に対しても慎重になります。
変化には反対勢力がいて、それは自分を守ったり、安全にすすめようとする力であることを理解すると「徹底的に」変えようとするよりも、無理のない範囲で行動を変えていく方が継続しやすいことがわかります。
なので、習慣も全部変えようとするよりも、少しずつ変えていく方がうまくいく可能性が高いです。
まとめ
動けない大きな理由は「やらなきゃ」になってしまうことです。
「自分はダメだから何かしよう、自分を変えよう」というのは行動するたびに自分を否定する苦しいやり方です。
最初は良くてもだんだん動けなくなってきます。
これが「満足したら終わり」なんて言われる所以かもしれません。
確かに自分に満足できない感覚、自己否定をパワーに動いていると「満足したら終わり」です。
満足するとガス欠になるからです。
でも「楽しい」が原動力だったら、最初から満足しているし、ガス欠になることもなく、物事がどんどん展開していきます。
私もまとめて書いてみて「楽しいからやる、やりたいからやる」その原動力で自分の人生を描いていきたいと思いました。
共感してくださった方は、ぜひご一緒しましょう^^
ーーー
記事更新のお知らせや自分らしい人生を描くエッセンスはメルマガでも配信しています。
登録はこちらから
気軽に登録してくださいね!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




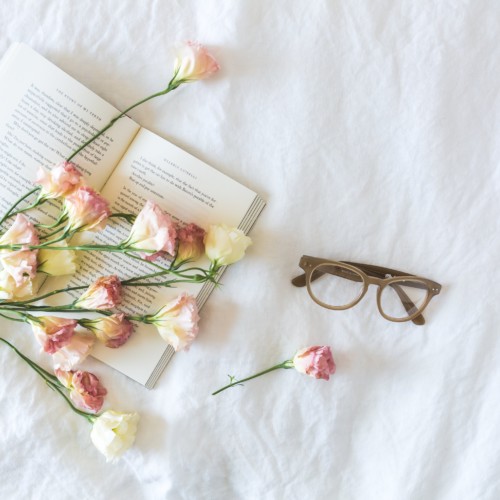







この記事へのコメントはありません。