心地よく人と関わり、素直に自分を表現できる「アサーティブコミュニケーション」とは?

人間関係やコミュニケーションってどうすればいいかよくわからなくて戸惑う、言いたいことが相手に言いづらい、自分の感情の整理がつかないまま話してしまう。
そんな経験ってありませんか?
私はありました。笑
コミュニケーションにはどちらかと言うと苦手意識がありました。
でも、出会った人と仲良くなったり、楽しい時間を過ごせたらいいなぁっていう想いもありました。
そんなときアサーティブコミュニケーションについて知って、コミュニケーションの目的や意義が明確になり、コミュニケーションってこういうためにあるんだ!となんだか安心しました。
そして、人と関わることを楽しめそうだなぁって思ったのを覚えています。
人間関係が苦手に感じるけど「誰かといる時間や空間を楽しみたい」と思うならぜひ知っておきたいコミュニケーションがアサーティブ・コミュニケーションです。
人間関係を円滑にしてくれるアサーティブ・コミュニケーションと、アサーティブ・コミュニケーションを実践していく時に必要な心の土台についてまとめました。
この記事の目次
コミュニケーションの4つの種類

アサーティブ(Assertive)とは自己主張するという意味です。
この自己主張をどのようにするかでコミュニケーションの種類を4つに分けることができます。
ノン・アサーティブコミュニケーション、アグレッシブ・コミュニケーション、作為的コミュニケーション、アサーティブ・コミュニケーションの4つです。それぞれ細かく見ていきます。
ノン・アサーティブコミュニケーション
自分の考え方や意見を主張しない、受け身のコミュニケーションです。
自分より相手を尊重し、自分を二の次にしてしまう態度です。
選択や決断を相手に任せてしまうことが多く、相手の意見をそのまま受け入れることで相手が不安になったり、相手に思い通りになる人間だと思われる傾向があります。
そのため気がつくと被害者的な立場になっていることもあります。
自らのコミュニケーションがその立ち位置を招いています。
アグレッシブ・コミュニケーション
自分の考え方や意見を相手への尊重なしに優先させてしまう一方的なコミュニケーションです。
自分の意見を押し通すために、威嚇したり、論理的でないことを言ったり、逆に正論で押し通したりしてしまいます。
その場では自分の意見を通すことができても周りにはあまり関わりたくない人と思われてしまうかもしれません。
言った後に言いすぎたと反省しているということもあります。
作為型コミュニケーション
言いたいことを言葉ではなく態度で示すタイプもあります。
なんとなく態度で示して相手をコントロールするコミュニケーションです。
不機嫌になることで嫌だという気持ちを伝えるなどがここにあたります。
また素直に依頼せず、嫌味を言うケースもあります。
「大変だから手伝って」ではなく「暇な人はいいよね〜」なんて言ってしまう感じです。
アサーティブ・コミュニケーション
自分の考え方や意見を主張しつつも相手のことも尊重するコミュニケーションです。
自分のことも大切にできますが、同じように相手のことも大切にできます。
我慢せずに言いずらいことでも伝えられて、それでいて相手も大切にできて、さらに関係性もよくなっていく画期的なコミュニケーションです。
アサーティブ・コミュニケーションのやりかた
ここまで読んで、4つのうちどれかを選べるなら、アサーティブコミュニケーションですよね。笑
そう思う方のために具体的にどんなふうにするのか、3つのステップと4つのポイントをご紹介します。
ステップ1 客観的に物事を把握
まず、誰が見ても分かる客観的事実だけを整理します。
忙しい時に仕事を頼まれた場合「仕事を頼まれた」「自分の仕事は納期が今週までのものがある」などが事実になります。
自分ばかり頼まれる気がする、暇だと思われていると思う、というのは客観的事実には入りません。
感情的になっているとなかなか客観的になれないことも多いですよね。
そういう時は少し落ち着いてから紙に書くなどしてみてもいいかもしれません。
ステップ2 感情と主張を整理
ステップ1 で整理した客観的な物事に対して自分はどう思っているのか、どう感じているのかを言葉にしておきます。
「納期が今週の仕事があるので忙しい。今頼まれた仕事をするのは難しいと感じる」「対応できるか不安」などです。
また、相手にどうしてほしいかも合わせて言葉にします。
「今回は別の人に頼んでほしい」「来週まで待ってほしい」などです。
ステップ3 相手に伝える
これを相手に伝えます。
ポイントは必ず主語を自分にすることです。
「私は今週納期の仕事があって、頼まれた仕事を今するのは難しいです。今回は別の方にお願いしてもらえませんか?」もしくは「来週まで待ってもらえたらできるんですが…どうでしょうか?」などです。
「あなたはいつも私に仕事を頼んでくるけど…」などと相手を主語にするとややこしいことになります。
もう一つ、相手に断るスペースを用意しておきます。疑問文で提案する、相手の返事を待つなどの態度がコミュニケーションをスムーズにします。
アサーティブコミュニケーション4つのポイント
アサーティブ・コミュニケーションでは4つ大切にしているポイントがあります。
①「誠実」
自分自身に正直になることで相手にも誠実になる
②「率直」
遠回しではなくストレートに、相手に伝わる言葉にする。
③「対等」
上から目線でも卑屈でもなく、態度も心の中も対等に向き合う。
④「自己責任」
言った責任、言わなかった責任は、自分が引き受ける
(特定非営利活動法人 アサーティブジャパン ホームページより)
この4つを真ん中におけば自然とコミュニケーションも態度もアサーティブになる言われています。
これらを大切にしながら性格ではなく伝え方を変ていくコミュニケーションがアサーティブコミュニケーションなのです。
アサーティブ・コミュニケーションを難しくするもの
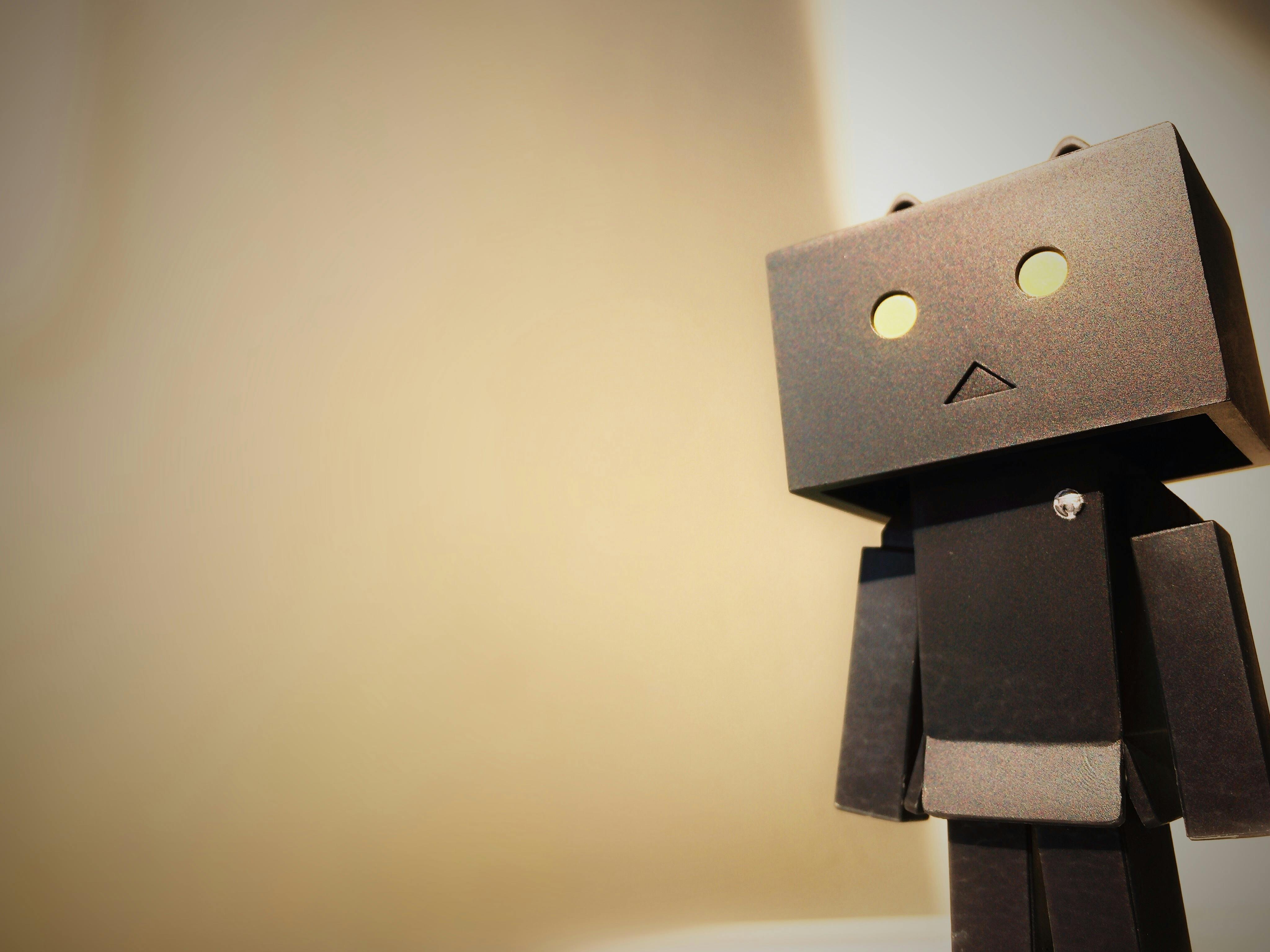
やり方がわかってもなかなかできない場合もあるかと思います。
アサーティブ・コミュニケーションでは事実を客観的に見ることが重要なので、正確に物事をとらえることを難しくする偏った考え方はアサーティブ・コミュニケーションを難しくしてしまいます。
ありがちな偏った考え方をご紹介します。
白黒思考
物事を白か黒かでとらえる極端な見方や考え方です。
オール・オア・ナッシング(All or Nothing)思考とも言われています。
0か100か、正しいか間違っているか、好きか嫌いか、など極端にものごとをとらえます。
このような偏った考え方をしていると、ひとつうまくいかないことや苦手なことがあると「自分には実力がない」「もううまくいかない」と落ち込んだり、うまくコミュニケーションが取れないことがあると「もうあの人とは仲良くなれない」と思い込んだりしてしまいます。
極端な一般化
ひとつの具体的な出来事を一般的な出来事だと解釈して、他の考え方を受け入れるスペースがなくなっている状態です。
仕事でミスをした人に対して「あの人は不注意な人だ」と決めつけてたり、逆に自分がミスをしたときに一度間違えてしまっただけなのに「いつもミスをする人だと思われるんじゃないか」と過度に心配になったりします。
悪いことに注目してしまう癖
悪いことにクローズアップして物事をとらえます。
白黒思考が影響していますが、嫌なことがあると今日はすごく嫌な1日だった!といいことを見れなくなる、ちょっと嫌な人はすごく嫌な人に見える、短所がある自分は長所があっても欠陥人間に感じる、などの一面的な判断に陥る可能性があります。
このように極端な考え方は客観的な状況把握を困難にします。
正当化する
自分を正当化しようとしているとものごとを客観的にとらえられません。
自分に都合のいい事実だけを見ようとするからです。
また、事実を歪めて認識してしまうこともあります。
正当化することで自分の本心を歪めたり、自分のことを否定的に見ることになるので結局自分のことも本当の意味では大切にできません。
なんのためにそんなことをするかというと、自分の存在価値を守るためです。
幼少期から親に認められるために自分を相手に合わせる、できた時や親の期待通りに動いた時にだけ認めてもらえるなどの条件付きの愛情を感じて育った場合、存在価値を感じるためにできる自分やいい自分を演じる必要があります。
自分の悪い部分やできていない部分を認めることはそうやって認められるために演じてきたできる自分やいい自分が壊れていくことです。
それは存在価値に関わる死活問題になります。
そうなると、どんな状況でも自分に非があってはいけない、なんとしても非を認めないということが必要なので自分を正当化をする傾向があります。
正当化するのは自分の評価を下げたくない、できなかったこと、悪かったことを認めたくないからですが、その裏には幼少期に身につけた習慣が関わっていることが多くあります。
アサーティブ・コミュニケーションを実践する土台

では、アサーティブ・コミュニケーションを実践するために必要なことはなんでしょうか。
キーワードは安心感
- 偏った見方をせずに客観的に物事を把握すること
- 自分を守ろうと正当化せず、事実を見ること
- 自分と相手を尊重する気持ちがある
- 自分も相手も大切にする気持ち
…あげたらきりがなさそうです。
ちょっと大変そうですね。
私は必要なことは、「安心感」この一言に尽きるのではないかと思います。
人と話す時に安心感を感じてリラックスしていられるかということです。
安心感があれば自然と周りを見渡して視野が広くなります。
安心感があれば自分を大切にできますし、同じように相手も大切にできます。
これは自分で自分のことをどこまで肯定しているかということと関わってきます。
自分へ肯定は成長過程で関わった親などの大人が自分をどれだけ認めてくれたと感じるかというのが影響します。
周りから認められると感じて育つと、自分はこれでいいんだ、自分には価値がある、何があっても大丈夫、なんとかなるという「安心感」を持つことができます。
これは自己肯定感と呼ぶこともあります。
逆に、周りの大人に自分は認められていない、自分には価値がないと感じて育つと安心感を感じることは難しくなります。
認められるためにやらなければならないことを多く抱えることになり、原動力は怖さなどのネガティブなものになります。
この状態だと自分を守ることにエネルギーを使い、内へと意識が行くので外の世界への興味は持ちにくく、その結果、視野も狭くなり反応的になります。
これが偏った見方や考え方の元になります。
安心感を手に入れるには?
人間関係が苦手分野だと感じて戸惑う、人と関わるのが怖いと感じてしまう、なかなかうまくいかない…その根底には傷付いた心(バーストラウマやインナーチャイルド)が原因で安心感がなかなか感じられない状態が関係している可能性があります。
安心感を手に入れるには自分は認められない人間だ、価値のない人間だ、という感覚のもとになっている心の傷を癒すのが有効です。
傷が癒えて、自分は価値がある人間なんだと自ら納得できることや自分で自分を認められることが安心感につながるからです。
傷を癒して、自分で自分を認めることができれば、安心感は大人になってからでも手に入れられるものです。
人と関わることをゆったり楽しんでみたい、自分を素直に表現するコミュニケーションをしたいそんな方は心の傷を癒すこと(バーストラウマやインナーチャイルドの癒し)を検討してみるといいかもしれません。
ーーーーーーー
人と関わることをもっと自由に、もっと面白く、もっと豊かにする「たまはな」を運営しています。
心地よく人と関わりたい人に向けて人と人との関係を心地よくして、人生をもっと楽しいものにするためのステップを紹介していきます。
質問に答えていくダイアリー形式で、自分の興味から、自分らしい人間関係を人げていくステップになっています。
自分のことがよくわからない人にもおすすめ。
ぜひのぞいて下さい^^
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。









この記事へのコメントはありません。