自分を生きるために欠かせない「受け入れる力」

本来の自分を見つけて、自分を生きるためには大切な力が3つあります。
自分のことがよくわからない、何がしたいが分からないという人は、大人になる過程でその3つの力を育むことが難しかったのかもしれません。
現代社会において、よくあることです。
その3つの大切な力の中でも重要な「自分を受け入れる力」について書こうと思います。自分を受け入れる力ってなんなのか、育んでいくにはどうしたらいいのかを書きます。
この記事の目次
自分の中の2人の自分

自分の中には2人の自分がいます。
自分と、自分を見ているもう1人の自分です。
「感情や感覚を感じている自分」に対してもう1人の「理性的な自分」が自分のことを見ています。
自分のことを見ている「理性的な自分」のキャラクターは幼い頃に関わった大人の影響を色濃く受け継ぎます。
多くの場合は親かと思いますが、否定的な親の場合は否定的な視線を取り込んで自分自身に向け続けることになります。
心配性の親の場合はその視線を取り込んで自分のことを心配し続けるということです。
具体的にはどういうことかというと「やることやってから遊びなさい」と言われれば大人になっても、自分を見ている「理性的な自分」が同じことを言うので「楽しいことはやるべきことを終わらせてからじゃないと」という発想になったり
「迷惑かけないようにね」と言われれば、実際に迷惑だと言われていなくても「迷惑かけてないかな…」と心配になります。
親に言われた言葉や向けられた視線はこのように自分にずっと向かい続けます。
私は幼い頃から習い事に行ったり、中学受験のために塾に通ったりしていました。
親の目線を感じて「勉強しなきゃ」とよく思っていたので受験勉強が終わっても心のどこかでいつも「ちゃんとやらなきゃ」と思っていました。
受け入れる力

「自分らしくいる」「自分を生きる」ということを考えた時に、重要なのは見ている「理性的な自分」が「感情や感覚を感じている自分」に対して肯定的であるかどうかです。
「自分らしく」とか「本当の自分でいる」というのは自分の感じていることや感覚をありのまま把握できること、そしてそれを受け入れられることだからです。
悲しいときに「悲しいんだね」、嬉しいときに「嬉しいんだね」と肯定的に受け止められるということです。
心理学では自己受容と言います。
自分を見ている「理性的な自分」が否定的だとなかなか自分の感じていることに素直になることができず、目の前のことに対して「どう感じているかがわからない」状態になる傾向があります。
例えば私は「もっと人に気を使いなさい」とか「人のことも考えなさい」とかたくさん言われて育ちました。
だから同じことを自分に言い続けました。
「気を使わないと」「相手のこともちゃんと考えられてるかなぁ」と心配になりました。
そして、自分の気持ちを相手に伝える前に相手の都合を考えるようになりました。
クセのようなものなので無意識にやっていることが多いです。
結果、目の前のことに対する自分の意見や本音はよくわからなくなってしまうこともありますし、本音を我慢したままコミュニケーションをとるのでどこかで歪みが生まれます。
見ている自分「理性的な自分」は言われた言葉だけでなく、親の目線も取り込んでいきます。
「宿題やったのかな」
「学校でうまくやれてるのかな」
「もっとこんな風にしないと」
そのままで認められない、干渉するような目線は自分への信頼感の欠如や「こんな自分でいいのかな」という否定感になって残ります。
否定感が残ったままだと自分が感じたことに対して、「理性的な自分」が騒ぎます。
「こんな風に感じる自分はずるいんじゃないか」「ダメなんじゃないか」「このままだと嫌われるんじゃないか」という不安や恐れを感じて、本当に感じていることが消えてしまいます。
だから自分を見ている「理性的な自分」を肯定的で受容的なキャラクターにしていくことが自分の感情や感覚をありのまま把握して、自分を生きる重要な力になります。
受け入れる力が育まれれば、本音は本音のまま大切にされます。
そうすれば、自分が本当に満足することを自分に与えることができるし、やりたいことを素直にやることが自然になってきます。
まずは自分に厳しくなっている時に気付こう

「理性的な自分」を受容的なキャラクターしていくには少し時間がかかります。根気強さも必要かもしれません。
まずは自分に厳しい目線をミケていることに気がつくことからはじめてみることをおすすめします。
どんな時に自分に厳しい目線を向けているのか、いくつかよくある例をご紹介します。
1.言い訳や正当性を考えている時
言い訳や正当性を考えている時、自分を責める自分がいます。
責められなければ言い訳や正当性は必要ないのです。
例えば何かが思ったようにできなかった時に言い訳を考えるかもしれません。
でも、できなかったことに対して本当はどう感じているのでしょうか?
できなくて悔しいとか、がんばったのに残念、悲しいとかそういう気持ちもあるかもしれません。
2.同じことをぐるぐる考えている時
同じことをぐるぐる考えている時もう少し深いところに本当の気持ちがあるのかもしれません。
不安な気持ちや気がかりなこと、見たくないことがある可能性もあります。
3.言いたいことがよくわからなくなる時
本音がキャッチできないと言いたいことはよくわからなくなります。
頭で作った「言うべきこと」は時間が経つと少しずつ忘れていきますし、最終的によくわからなくなってしまうことがあります。
話しているうちに言いたいことや自分の意見がよくわからなくなってしまうとき、人目を気にして自分のことを制御しながら話していませんか?
受け入れる力の育み方
厳しい目線を向けている自分に気がついたら、受け入れる力を育んでいきたいと感じる方も多いと思います。
ここからは受け入れる力の育み方について書いてみます。
1.否定的になっている自分を受け入れる
「否定されている自分」も、「否定している自分」もどちらも自分です。
「否定されている自分」が大切で、「否定している自分」は悪者というわけではありません。
まずは否定していることを認めることからはじめます。
認めるというというより感覚的にはただ認識するだけ、という感じです。
「あ、いま否定的になってるんだな」と気がついて、一方で温かく見守り、一方であきらめるという感じです。
なんとかしようとしないのがポイントです。
実際の人間関係でもなんとかしようとあれこれ口出しされたりすると反発したくなることってありませんか?
なんとかしようとしない、もしくは何か否定してしまう理由があるんだなと思って、その理由は棚上げしておきます。
自然とわかる時がくるから、今は扱う必要はありません。
無理に扱うと思考が働くのでより、自分が感じていることがキャッチしづらくなってしまいます。
2.否定されている自分に目を向けてみる
不思議なんですが「否定している自分」を見つけて、否定していること自体を受け入れることができると否定感が緩んできます。
そうしたら次は「否定されている自分」が何を感じていたか目を向けてみます。
否定されたら悲しいですよね。
本当は言いたいこととかなかったでしょうか?
最初はあんまりよくわからないかもしれません。
とりあえず「どんなこと感じてるんだろ〜」くらい軽い感じで意識を向けて日常生活を送ってみてください。ふと、本当の気持ちが顔を出す時もあります。
もし聞こえたら、受容的な言葉をかけてあげてください。
悲しんでいたら「そうだよね、それは悲しいよね」という感じです。
怒っていたら「こんなんで怒るなんて心が狭い」とか「くだらない」なんて言わずに「そうだね。それは腹がたつよね。」です。

ポイント
やることは基本的にはこの2つです。
どちらの声も聞いて、ただただ認識する。
ちょっとイメージしずらいかもしれませんが、ただ認識するのってこういう感じです。
「あ、否定してる!」と気づく。
次の瞬間、じゃぁ、今どうかを認識する。
「まだ否定してる」とわかる。
また次の瞬間どうかを認識する。
「あ、まだ否定してる」と気づく。
これをエンドレスでやる感じです。
よくあるのはここで、何を否定してるんだろうとか、どうして否定してるんだろうとか、否定しないようにするには…とか考え出してしまうことです。
どうか、考えないでください。
けっこう難しいですが、ここがブレイクスルーのポイントになります。
諦められるかというのはひとつの重要な要素なのです。
諦めることはコントロールしないことにつながり、コントロールしないことは信頼するということだからです。
そして、気長にゆっくり、は大切です。
否定感というのは一気に消えるものではなくて段階的に緩くなって肯定感に反転していきます。
「なんだかすごく手放せた!軽〜い!」と喜んでいる1ヶ月後には新たな否定感を感じているなんて残念ですが、いたって普通です。
新しい否定感を感じるとなんだか前に進んでないような気もするかもしれませんがそんなことありません。
ちゃんと認めた分だけ自分に肯定的になっているし、うまくできなくても自分への理解は少しずつ確実に深まっています。
おわりに
自分を受け入れていくというのは自分を知って世界を広げるということです。
それは今まで否定してないことにしていた自分の一部に、存在するためのスペースを与えることです。
否定感が肯定感になるというのはそういうことです。
そうやって世界が広がることで本来の自分が顔を出します。
自分の本当の人生の始まりです。
否定感を肯定感に変えて、自分らしい人生を描きましょう。

コメント ( 2 )
トラックバックは利用できません。











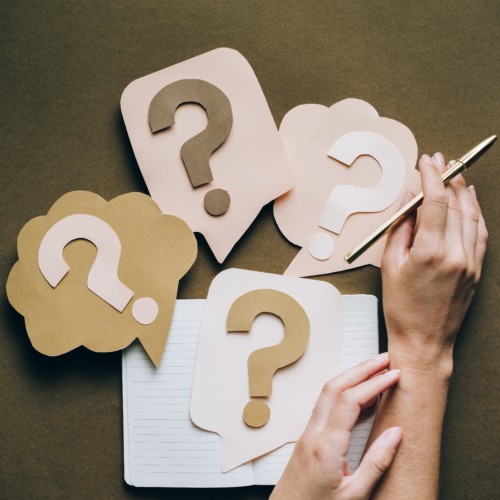
こんにちは
こちらの記事に今救われました。ありがとうございます。
こんにちは。コメントありがとうございます。お役に立てたようで嬉しいです。